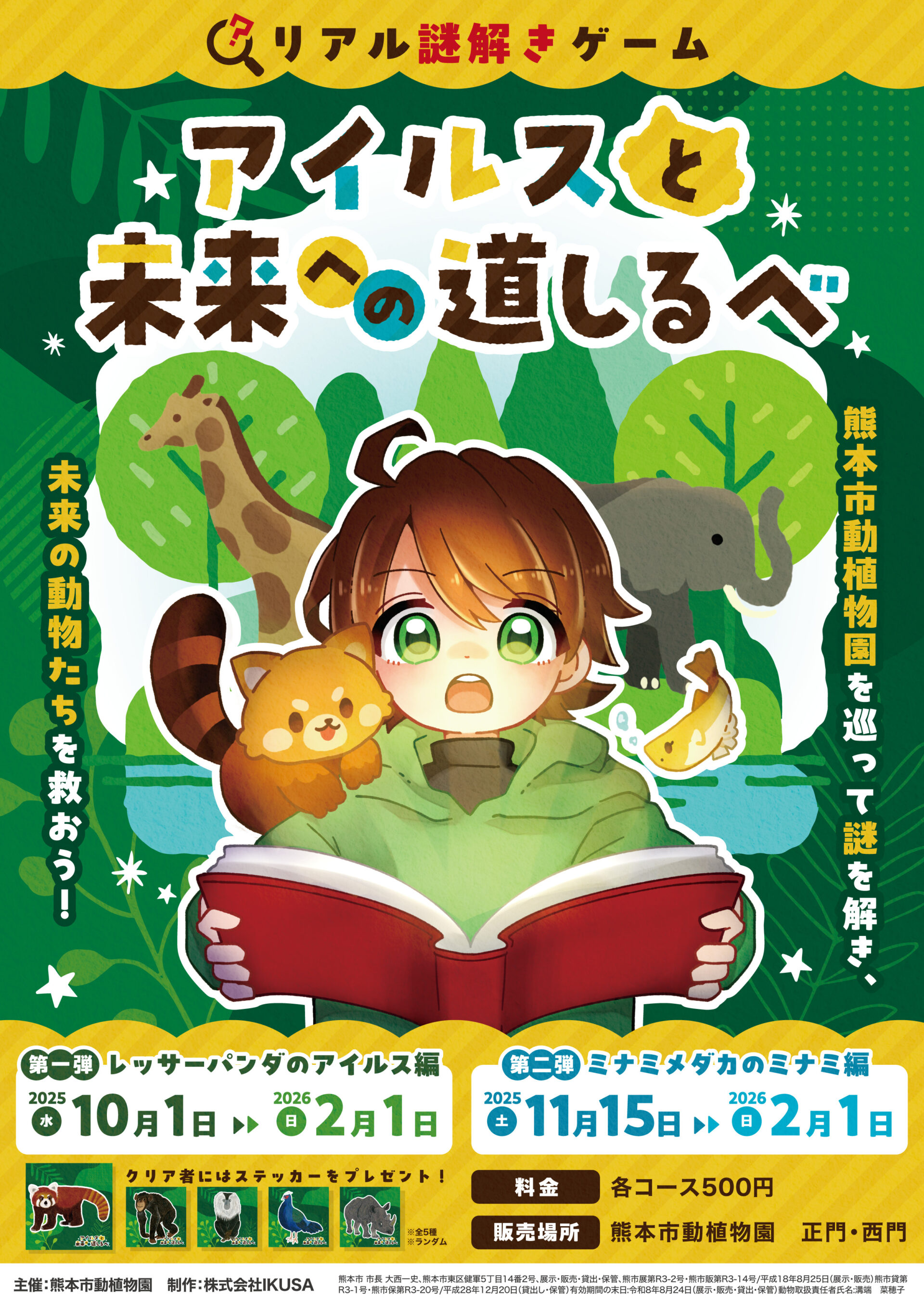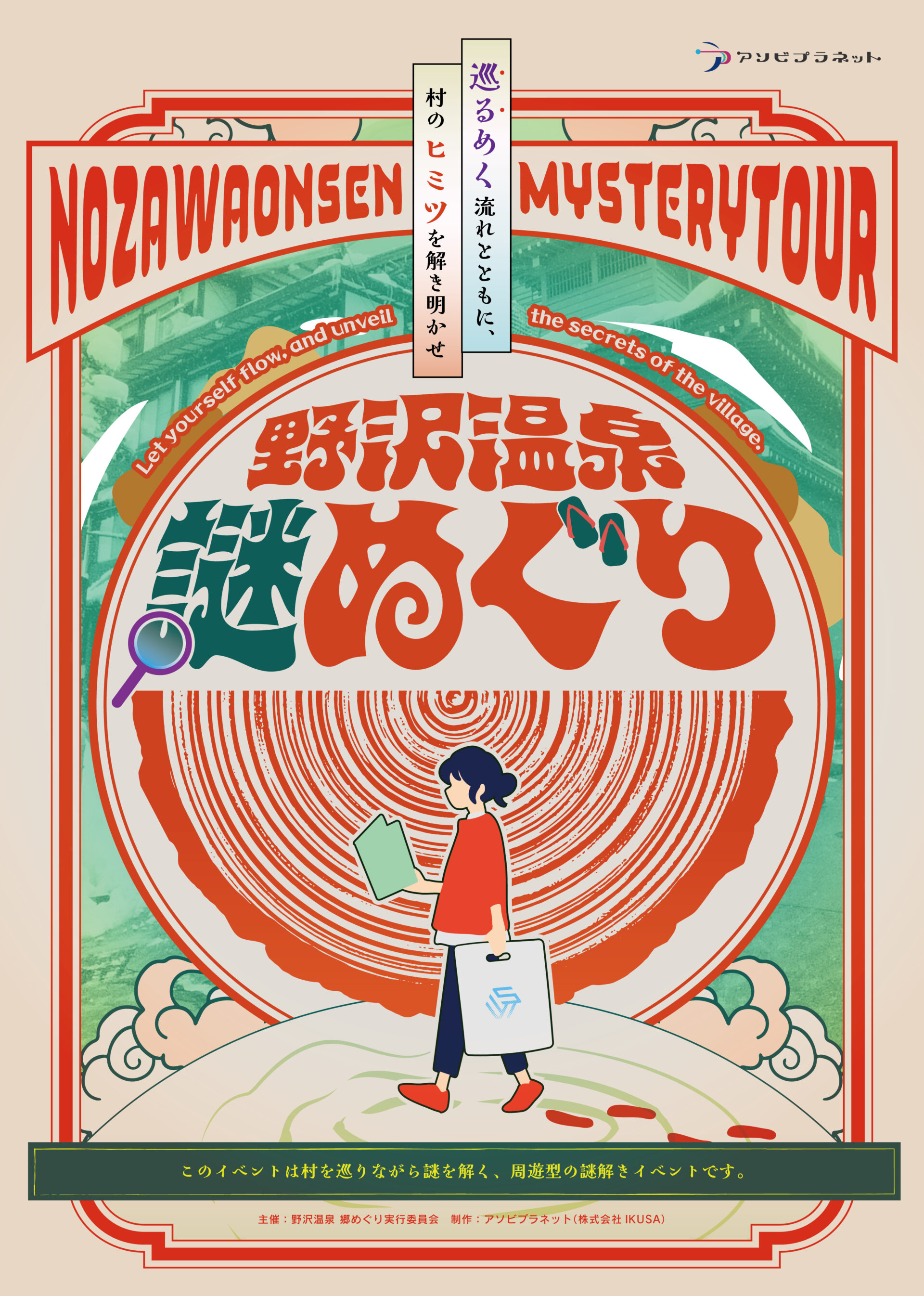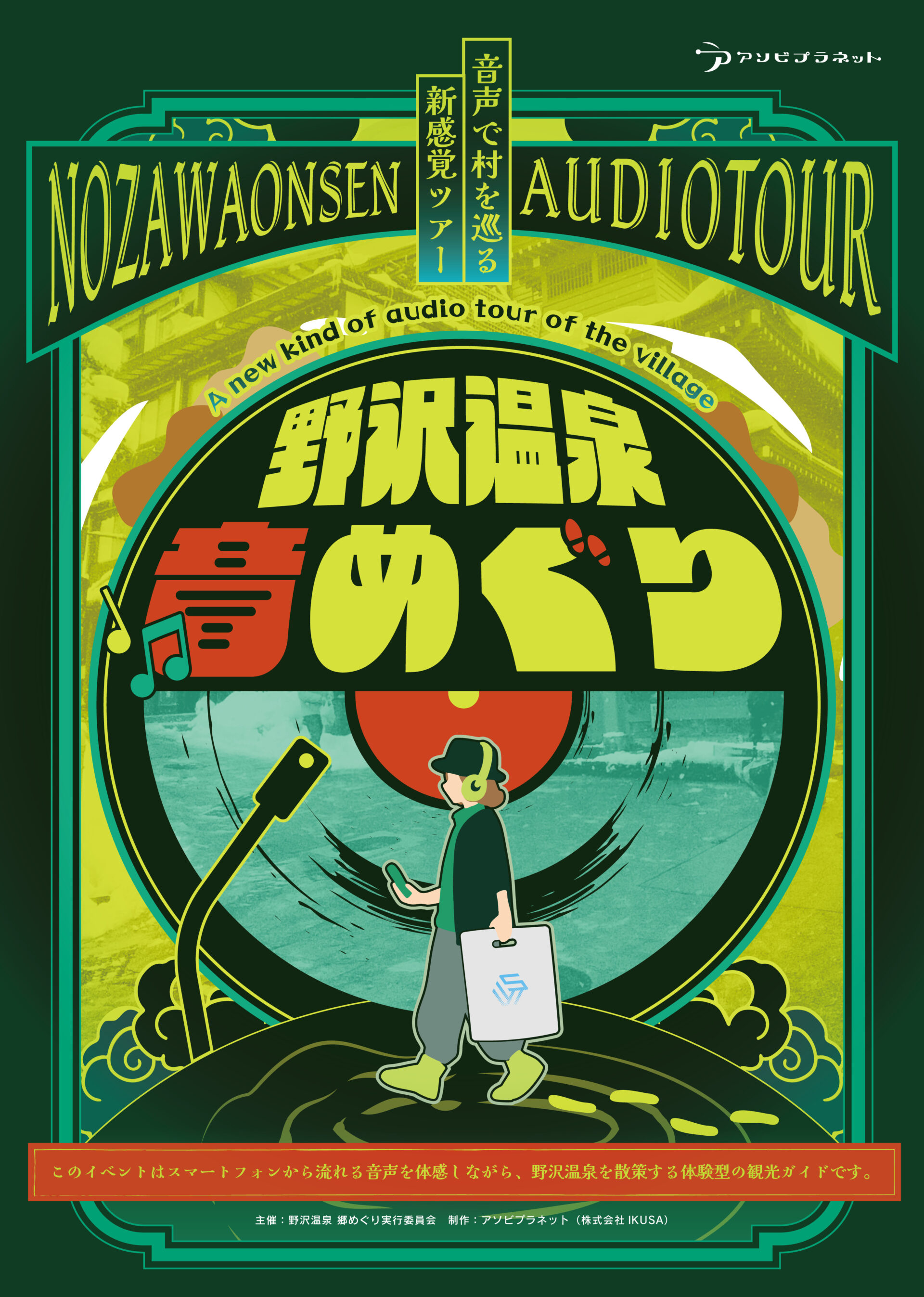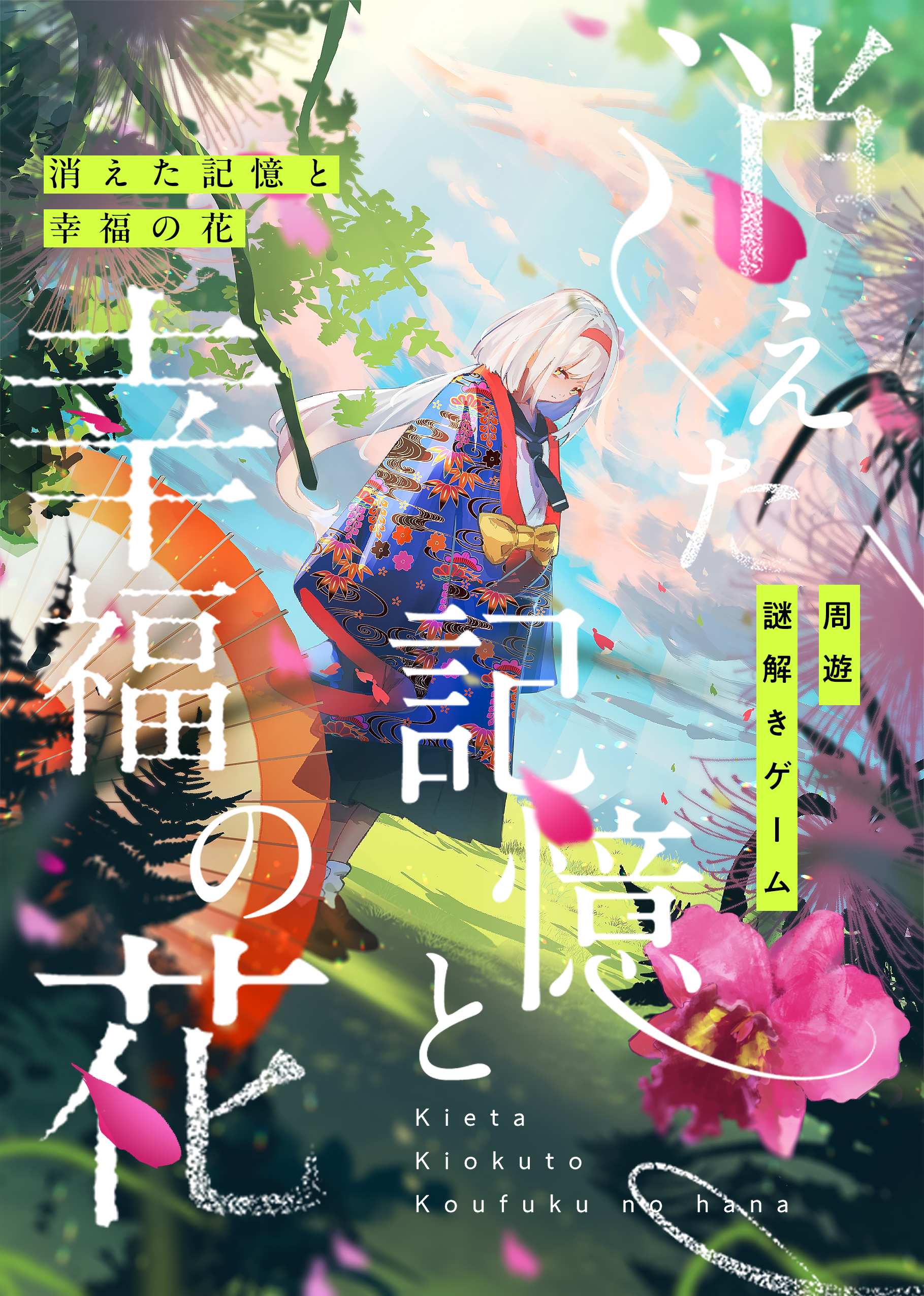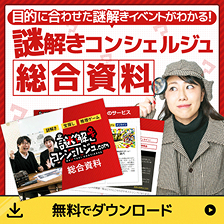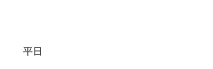お困りごとはいつでも
ご相談ください二ャ
謎解きコンシェルジュキャラクター「シェルジュ」

チームビルディング
クイズ制作の方法を解説!制作に役立つツールも紹介
- 謎解き


目次
社内企画やイベント、学校行事などを盛り上げるために「クイズ」は有効なコンテンツの一つです。しかし、いざクイズを制作しようと思っても、どのようなテーマで、どのような問題を作るか、どのような流れで進めればよいのか迷うこともあるかもしれません。
アイデアを形にして楽しいクイズを作るためのヒントとなるように、本記事では、クイズ制作の基本ステップ、クイズ制作のポイント、クイズ制作に役立つツールを紹介します。
目的やターゲットにあった謎解きイベントが見つかる!
謎解き・推理ゲームを活用した参加型企画の資料を無料配布中
⇒無料で資料を受け取る
クイズを制作する際の基本ステップ
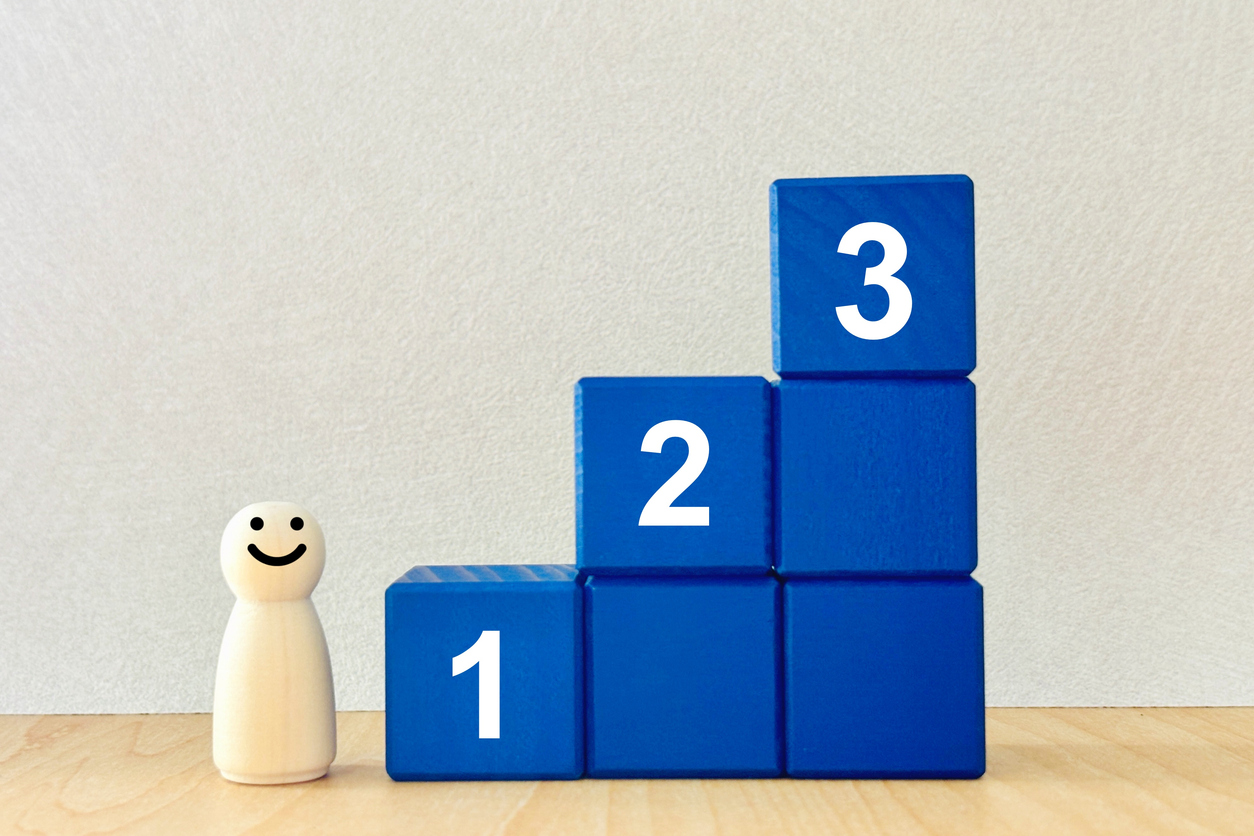
クイズの作り方に決まりはありませんが、手順に沿って進めるとスムーズです。クイズを制作する際の基本ステップを押さえておきましょう。
1.目的やターゲットを決める
まずは「クイズ制作の目的」と「誰に向けて出題するのか」をはっきりさせることが重要です。
交流会の催しの一環で盛り上がるために使うのか、子どもに楽しんでもらうのか、研修やイベントのアイスブレイクに活用するのか、その目的によって、クイズの方向性や問題数は変わります。
その際、クイズを解くターゲットを具体的にイメージすることが大切です。大人向けなのか、子ども向けなのか、専門知識を持つ人向けなのかによって、適切な言葉遣いや難易度も変わってきます。
たとえば、子ども向けなら簡単な表現や身近な話題を選ぶと理解しやすく、大人向けなら時事性や専門性を加えることで盛り上がりやすくなります。
目的やターゲットを曖昧にしたまま進めてしまうと、適切な問題数や難易度になりづらく、方向性にズレが生じやすくなるため、最初の段階で丁寧に整理しておきましょう。
2.出題形式を決める
目的とターゲットが決まったら、それに合わせたクイズの出題形式や構成を考えます。同じ形式ばかりが続くと単調になりやすいため、複数の形式を組み合わせるのがおすすめです。
代表的な形式について以下で解説します。
早押しクイズ
早押しクイズは、出題を聞いて答えがわかった時点でボタンを押し、一番早く押した人が解答権を得るクイズです。知識だけでなく瞬発力も試されるため、競技性が高く、緊張感と相まって盛り上がりやすいでしょう。
また、後述する四択クイズや○×クイズなど他の形式と並行しておこなえるのも特徴です。たとえば「四択問題を早押しで答える」とすれば、四択への推理や知識、そしてスピード勝負を楽しめます。参加者同士の競争を重視したい場面や、緩急をつけたいときにおすすめです。
四択クイズ
定番のスタイルともいえるのが四択クイズです。複数の選択肢の中から答えを選ぶ形式なので参加しやすく、知識を試す問題から雑学まで、題材を問わずに使えるクイズといえるでしょう。
選択肢数は四つが基本ですが、作問の手間や進行スピードを考えて三択にするのも一つの方法です。また、単に正解を一つ混ぜるだけではなく、ハズレの選択肢から推理できるようにしたり、ユーモアのある選択肢を加えたりすることで、知識差を埋めながら誰でも楽しめる工夫ができます。
○×クイズ
○×クイズは、ある事実や情報に対して「正しいか」「間違っているか」を答えるシンプルな形式のクイズです。
直感的に答えられるためテンポよく進み、大人数でも同時に楽しめます。特に低年齢層が参加する場面でも、50%の確率で正解できるため、問題がわからなくても運試しとしても楽しむことができ、気軽に参加しやすい魅力があります。
記述クイズ
記述クイズとは、選択肢が提示されず、回答者が自分の知識を頼りに紙やボードに回答を書いて公開するクイズです。
答えが思い浮かばなければ書けないため、他の形式よりも難易度は高くなりやすいものの、正解したときの達成感は大きく、知識勝負を重視する際に盛り上がりやすいでしょう。
記述クイズは、参加者の知識レベルに差が大きいと優劣がつきすぎてしまうため、全員で楽しむ場面では部分的に取り入れる程度がよいでしょう。
穴埋めクイズ
穴埋めクイズは、文章やフレーズの一部を空欄にして、そこに当てはまる言葉を答えるクイズです。
単語や数字を答えたり、ことわざや名言の一部を隠して当てるといった幅広い楽しみ方が可能です。問題文全体を読むことでヒントを推測できるため、知識勝負だけでなく、発想力や文脈を理解する力があれば回答できる可能性があります。
言葉遊び的な要素を取り入れやすく、小中学生向けの学習クイズや、アイスブレイクにも適しています。
写真・音声クイズ
写真・音声クイズは、画像や音声を提示し、それを手掛かりに問題に答えるクイズです。人物や建物の写真、動物の鳴き声などから「これはなにを表しているでしょう?」「これは何の鳴き声でしょう?」といった出題ができ、言葉だけでは表現しづらい題材を扱える点が特徴です。
見るだけ、聞くだけといった要素から気軽に参加でき、パーティーやイベントで盛り上げたいときにも向いています。
3.問題を作成する
出題形式まで固まったら、実際に問題を作成していきます。まずは題材に関する情報収集をおこない、信頼できるソースから正確な知識を集めることが基本です。そのうえで、参加者のレベルに合った問題を考えましょう。
冗長な説明や複雑な言い回しは避け、問題文はできるだけ簡潔で明快にすることを意識し、誰が読んでも理解できるようにしましょう。
4.答えに対する解説を用意する
クイズは問いと答えだけでなく、その答えに納得できる解説も用意しておきましょう。たとえば「正解は○○です」と告げるだけではあっさり終わってしまいますが、「○○はもともと□□が由来で、意外な歴史的背景がある」といった解説を添えることで、不正解であっても納得度が増し、クイズを単なる正誤判定にせず、知識を得る場としても盛り上がります。
5.難易度を調整する
出題する問題の難易度は、参加者に合わせて設計する必要があります。あまりに簡単すぎると物足りなさを感じさせ、難しすぎるとやる気がそがれてしまいます。
例えば、全体の中で簡単な問題を三割程度、標準的な問題を五割程度、やや難しい問題を二割程度の割合で構成すると、多くの人が適度に考え、適度に正解できるバランスになるでしょう。
ただし、難易度のバランスに正解はありません。たとえば、交流やアイスブレイクの場といった「競い合いを目的としない」場合は、全体的に難易度を下げ、誰もが一問は正解できるような設計にしておくと安心感が生まれ、楽しさにつながります。
6.テストプレイをしてみる
難易度調整まで終えても、そのまま本番に使うのではなく、テストプレイしてみることが大切です。その際は友人や家族など、身近な人に試してもらい、フィードバックをもらうのが有効です。
また、答えを知っている出題者やクイズ制作チームで実際にテストプレイしてみることも重要です。実際の形式に沿って一通り解いてみると、「思ったより時間がかかる」「この問題だけ突出して難しい」といった感覚的な課題に気づくことがあります。本番同様のプレイ感覚を体験することで、難易度の調整や構成の改善につながります。
7.出題するフォーマットを決める
クイズをどのように出題するのか、フォーマットを決めます。紙に印刷して配布する方法もあれば、スライドにまとめて投影する方法、オンラインのクイズツールを活用して出題する方法などもあります。
フォーマットによって準備の手間や進行のテンポが変わるため、遊ぶ環境に合わせて選ぶことが重要です。
クイズ制作のポイント

基本のステップを踏まえて、クイズ制作において押さえておきたいポイントを紹介します。
クイズとして成立することを念頭に置く
クイズで最も避けたいのは、問題と解答に誤りが含まれて「クイズとして成立しない」状況になることです。
回答者から誤りを指摘されれば、その場の空気が冷めてしまうだけでなく、「この先の問題にも間違いがあるのではないか」と不安を抱かせてしまいます。逆に誤りが指摘されなければ、間違った知識を参加者全員に広めることにもつながります。
こうしたリスクを避けるためには、必ず問題と解答の事実確認を行うことが大切です。インターネットで調べる場合も、ひとつのサイトだけを根拠にせず、複数の情報源から検討しましょう。さらに可能であれば一次情報にあたることで、クイズとしての正確性と信頼性を高められます。
また、「情報が古くなっていないか」という点も気にしましょう。特にスポーツの記録、制度や法律、人口や統計などは時間の経過によって正解が変わる可能性があるため、制作時には必ず最新の情報に更新されているかを確認し、答えが現時点でも有効であることを確かめることが大切です。
正解が一つに定まるようにする
クイズは「答えがはっきり一つに定まる」ことで成立します。「一説によると」「諸説あり」といった解説が必要になる題材は、そのままではクイズに適さないことがあります。
どうしても複数の答えが存在する場合は、設問の仕方を工夫して「どれも正解」とできるようにしたり、複数回答を求める形式にするなど、回答者が納得感を持てる形にしましょう。
問題文をそろえる
複数の問題文の文体をそろえることもクイズ制作におけるポイントのひとつです。
問題そのものが優れていても、文体がバラバラだと出題のテンポに一貫性がなくなり、問題を読む人にとっても、回答者にとって解きにくいクイズになってしまいます。
たとえば「この人物は誰でしょう?」という聞き方と、「○○を行ったのは誰か」という聞き方が混在していると、毎回読み方のリズムが変わり、余計なストレスを与えてしまいます。文字数語尾や表記を統一するだけでも、全体の印象が整理され、クイズへの没入感が高まります。
問題数と時間配分を考慮する
クイズの面白さを左右する大きな要素のひとつがテンポです。いくら面白い問題を用意しても、時間が余ったり、逆に押してしまったりすると、場の盛り上がりは途切れてしまいます。
実際のクイズの時間を想定し、問題数や1問あたりの解答時間を設計しておきましょう。途中で間延びしないように調整すれば、参加者の集中力を保ったまま最後まで楽しんでもらうことにつながります。
表記の視認性を重視する
クイズは「問題を正しく理解できるか」が出発点です。スライドや印刷物で出題する場合、フォントの大きさや色、文字間隔など、視認性を意識したデザインにすることが重要です。
小さすぎる文字や紛らわしい色やフォントは、誤読や見落としにつながります。誰が見てもすぐに理解できる表記を心がけるようにしましょう。
答えにたどり着ける工夫をする
難しすぎる問題や、答えにたどり着けないような問題は参加者のモチベーションを下げてしまいます。とはいえ、難しい問題そのものが悪いわけではありません。
たとえば、答えの推理ができる選択肢を設けたり、ヒントを段階的に提示したりすることで、「考えてわかる」体験を作ることができます。難しい問題やひねりの効いた問題を作るときこそ、答えにたどり着けるような工夫を用意しましょう。
クイズ制作に役立つツール

クイズ制作の際には、問題の作成はもちろん、自分で誰かに披露するのであれば見た目のデザインや出題の進行まで考える必要があります。
こうした作業を効率よく進めるためには、ツールを使うのがおすすめです。ここでは、クイズ制作をサポートしてくれる身近なツールを紹介します。
Googleフォーム
手軽にクイズを作れるのがGoogleフォームです。問題を入力し、回答を設定することで選択肢形式や○×形式のクイズが作成でき、正解設定も簡単におこなえます。
問題ごとの点数設定や、回答へのフィードバック機能を使って解説も入れることができるほか、回答結果の集計も可能です。オンラインで共有できるので、大人数のイベントでも活用でき、遠隔地にいる参加者とのクイズ大会にも向いています。
PowerPoint
プレゼンテーションソフトウェアであるPowerPointも、クイズ制作で活用できます。スライドに問題文と選択肢を載せ、正解のページへジャンプするリンクを設定することで、簡単にクイズが作成できます。
加えて、タイトルとなるスライドやルール説明、各問題への解説やクイズ全体のまとめといったスライドも作成でき、より細かい演出を作り込めるため、しっかりとしたクイズ進行に利用できます。
オフラインの会場や学校行事など、プロジェクターで投影して進行する場面で特に使いやすいツールです。
Canva
Canvaは、教育現場やイベント、研修など幅広いシーンで活用できるオンラインデザインツールです。
クイズ用テンプレートが用意されており、学習系のテストから、イベントのアイスブレイクまで、テーマに応じたクイズを作成できます。好きなテンプレートを選び、問題を設定していくだけで簡単にクイズを作成できます。また、選択式、○×、穴埋めクイズといった多様な出題形式で作成することが可能です。
クイズは、パソコンはもちろん、スマホアプリからも編集可能で、外出先で問題の修正やデザインの調整ができます。作成したクイズはオンラインで配布・共有できます。
Excel・Googleスプレッドシート
クイズの問題を体系的に整理するには、ExcelやGoogleスプレッドシートが便利です。
問題文、選択肢、正解、解説といった要素を行ごとにまとめておくことで、作成途中でも問題全体を把握しやすくなります。
さらに、検索・並べ替え機能を活用すれば、たとえば「ジャンルごとに並べ替えて構成を確認する」「難易度の偏りのある問題群を見直す」といった使い方が可能です。
こうして整理しておけば、後で問題を修正したり新しい問題を追加したりする際も効率的に対応できます。
QuizGenerator
QuizGeneratorは、プログラミングの知識がなくても簡単にクイズ制作がおこなえるツールです。
出題形式は選択クイズ・○×問題・記述クイズ・穴埋めクイズなど13種類を備えており、幅広いシーンに対応できます。加えて、時間制限のあるテストモードや、すべて解き終わった後に採点する設定、一定時間ごとに自動で次の問題に切り替える仕組みなど、細かな機能も揃っています。
作成方法も、Web上のフォームから入力する方法のほか、テキストやExcelを使って問題を一括登録することも可能です。また、作成したクイズはWeb上で限定公開・一般公開を選べるほか、自分のブログやWebサイトに埋め込むこともできます。
商用・個人利用ともに無料で活用でき、ライセンスを購入すればデザイン変更やクレジット表記の削除ができます。
まとめ

クイズ制作は、目的やターゲットの整理から始まり、出題形式の選定、問題作成、解説の追加、難易度調整、テストプレイ、フォーマット決めといったステップを経て、完成に近づけていきます。また、問題を作る際には「正解が一つに定まるか」「問題文が統一されているか」といったポイントをおさえておくことも重要です。
クイズは事実をもとにした出題である以上、正確性が最優先ですが、それだけでは魅力あるものになりません。問題文の表現や構成、出題形式の組み合わせ、難易度や全体のバランスなど、総合的な創作性が問われます。知識をただ並べるのではなく、「どう出題すれば盛り上がるか」「どうすれば最後まで飽きずに楽しめるか」といった工夫が重要です。
今回紹介した基本ステップとポイントを押さえ、ツールをうまく活用しながら、魅力的なクイズを作ってみてください。
謎解きコンシェルジュは、企業・自治体・施設・学校などで活用できる謎解きイベントの企画・運営を行っています。ユニークな謎解きイベントの企画をお探しの方はぜひ資料をご覧ください。
⇒謎解きイベント企画資料を受け取る